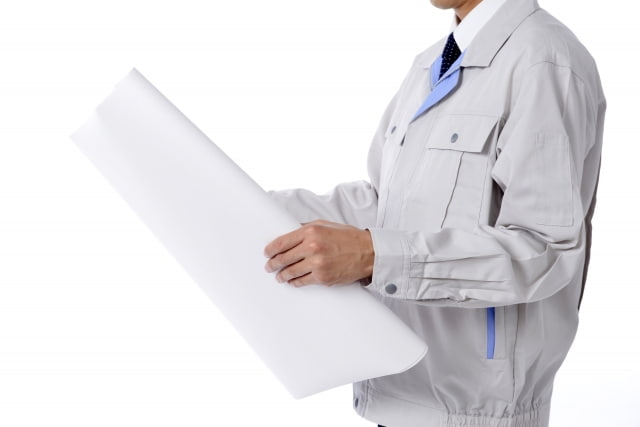関西地域における特殊建築物の定期調査報告制度とは?
学校やデパート、劇場などの公共性の高い「特殊建築物」には定期的に調査と報告を行う義務が課されています。また特殊建築物の定期調査報告制度は地域によって詳細が異なっています。
当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかを見ていきます。
大阪府における特殊建築物の定期調査報告制度
1.大阪府における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
大阪府では特殊建築物の定期調査報告を大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の17か所の市と一般社団法人大阪建築防災センターで取り扱っています。
また昇降機等の定期報告は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会で取り扱っています。
故意的に調査、報告を既定の期間内に報告しなかった場合、100万円以下の罰金が科されつため、期限内にしっかりと定期報告を行いましょう。
2.大阪府における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
大阪府における対象となる特定建築物は学校、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、博物館、美術館、図書館、集会場、劇場、ホテル、旅館、病院、診療所、児童福祉施設等、百貨店、物販店舗、飲食店、共同住宅、その他サービス店とされています。
他県と異なり、学校やボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場及び給排水設備は調査・報告の対象外です。
3.大阪府における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は一般社団法人大阪建築防災センターのHPで入手できます。
ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。
ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入
ⅳ 特定行政庁に提出
また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。
4.注意点
ⅰ 支援サービス料
大阪府では特定建築物・特定建築設備の提出の際に、建物の規模によって3000円から15000円の支援サービス料がかかります。
ⅱ 報告期間
4月1日から12月25日まで。支援サービス料の早期提出割引の適用は4月1日から8月末まで。
兵庫県における特殊建築物の定期調査報告制度
1.兵庫県における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
兵庫県では特殊建築物の定期調査報告を神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市の12か所の市と公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターで取り扱っています。
2.兵庫県における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
兵庫県における対象となる特定建築物は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場、病院、診療所、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、事務所その他これに類するものとされています。
また建築設備、防火設備、昇降機等のほかにもブロック塀等の定期報告が必要です。
3.兵庫県における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 報告書をダウンロードする
報告書は兵庫県住宅建築総合センターのHPで入手できます。
ⅱ 調査
有資格者の場合は自分で調査を行います。
ⅲ 指定の報告書様式に調査結果を記入
ⅳ 特定行政庁に提出
また資格がない場合、専門の業者に委託すると、すべての作業をお任せすることができて便利です。
4.注意点
ⅰ 報告期間
7月から10月まで。
ⅱ 提出先
神戸市は市のみに提出先が限定されています。
関連記事:神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
神戸市における特殊建築物の定期調査報告制度
1.神戸市における特定建築物調査・特定建築設備調査の概要
神戸市は特殊建築物の定期調査報告の提出先が神戸市に限定されています。また定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者に対して、ステッカーが配布されます。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合、処分の対象になるため注意が必要です。
2.神戸市における対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告内容
劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場、病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎、ホテル、旅館、共同住宅、公衆浴場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、事務所その他これに類するものとされています。
3.神戸市における特定建築物・特定建築設備の報告方法
ⅰ 特殊建築物等定期調査報告書の入手
神戸市のHPからダウンロードします。
ⅱ 神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参する
神戸市では調査を行った有資格者が神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係に報告書を持参しなければいけません(代理不可)。
4.注意点
ⅰ 報告期間
8月1日から11月30日まで。
関連記事:兵庫県の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
まとめ
当記事では関西主要都市における特殊建築物の定期調査報告制度がどのように定められているのかをご紹介してきました。見てきたように特殊建築物の定期調査報告制度は地域で異なるため、調査・報告する準備段階でしっかりと自分の地域の特殊建築物の定期調査報告制度がどのようになっているのかを調べることが大事だといえます。
特殊建築物定期報告の概要と期間を詳しく解説
特殊建築物の定期報告には特殊建築物定期検査報告と防火設備定期検査報告、建築設備定期検査報告書、昇降機等定期検査報告があります。
特殊建築物定期報告は3年に1回の検査報告が必要で、防火設備定期検査報告、建築設備定期検査報告書、昇降機等定期検査報告は毎年の調査報告が必要となっています。
特殊建築物定期検査報告の詳細は各自治体によって変わります。
特殊建築物定期検査報告の概要
特殊建築物(特定建築物)調査は、建築基準法第12条によって定められている調査で、特定建築物は建築基準法第2条2項で定められている不特定多数の人が扱う公共性の高い建物が該当します。
なので、特殊建築物調査は戸建て住宅や事務所以外のほとんどの建物が該当し、調査結果によって経営や資産価値は大きく変わってきます。
調査内容は、「敷地・地盤」「建物外部」「屋上・屋根」「建物内部」「避難施設・非常用進入口」に分かれており、敷地・地盤のひび割れや損傷、排水が正しく行われているか、建物の外壁にひび割れや沈下がないか、屋上・屋根のひび割れや損傷、排水が正しく行われているか、建物内部の壁や床・天井に損傷はないか、避難経路は正しく行われているかなどを詳しく調査します。
調査方法は主に、目視とハンマーなどでたたいて確認し、建物の外部に関しては平成20年の建築基準法改正以降、打診・赤外線カメラ等による詳細な調査が必要となっています。
また、従来の基準では簡単な調査で報告を終わらせてる建物が多かったために自然災害や事故の際に重大な火災や崩落が相次いだために、特殊建築物定期検査報告は、平成24年から25年にかけて大幅に見なされ、定期報告の強化がされました。
特殊建築物定期検査報告の期間と報告年について
特殊建築物定期検査報告の期間は3年に1回で、用途ごとに報告年度が定められています。
建物の用途や各自治体(特定行政庁)によっては毎年調査する必要もあるので確認が必要です。
特殊建築物定期検査報告には建築設備と防火設備の調査項目があり、建築設備の調査は学校とボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場・体育館を除くすべての特殊建築物で毎年1回、防火設備の調査は全ての特定建築物で毎年1回の定期検査報告が必要となります。
報告年については、各都道府県によって異なるので、各都道府県のホームページより確認してください。
初回調査の免除と調査対象
戸建て住宅以外のほとんどの建物が該当する特殊建築物ですが、用途、規模によっては定期報告が免除されたり、定期調査の報告頻度が変わります。
新築の特殊建築物、又は改築後の特殊建築物については、検査済みの書類を受け取った日付が属する年度の特定建築物定期検査は免除され、翌年以降の報告時期から特定建築物定期検査報告が必要になります。
学校やボーリング場などのスポーツ練習場、博物館・美術館・図書館・集会場・劇場・観覧場・ホテル・病院・福祉施設・百貨店。飲食店・共同住宅は3階以上に対象用途があると、特殊建築物定期検査報告をする必要があり、3階以下の場合は特定建築物定期検査報告は必要ありません。
また、3階以下であっても、所要面積がオーバーしていると特定建築物定期検査報告を実施する必要があります。
学校やボーリング場などのスポーツ練習場・博物館・美術館・図書館は3階以下で床面積が2000㎡以内であれば特定建築物定期検査報告は必要なくなり、事務所は5階以下で床面積3000㎡以内であれば特定建築物定期検査報告は必要ありません。
共同住宅の場合は、3階以上に対象用途があり床面積1000㎡以上の場合、又は5階以上に対象用途があり床面積500㎡以上に当てはまらない構造だと特定建築物定期検査報告は必要ありません。
サービス付高齢者向け宿舎、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホーム、サービス付高齢者向け住宅の場合は、3階以上に用途がある場合、地下に対象用途がある場合、2階部分の対象用途の床面積が300㎡以上の場合のいずれかに当てはまると、特殊建築物定期検査報告が必要になります。
共同のサービス付き高齢者向け住宅や共同住宅の場合、非常用エレベーターが設置されていると建築設備の定期検査が必要で、共同住宅は非常用エレベーターが設置されていると防火設備定期検査が必要になります。
定期報告書類の保管期間
定期報告には特殊建築物定期検査報告、防火設備定期検査報告、建築設備定期検査報告書、昇降機等定期検査報告の4種類があり、報告書類の控えを保存する義務はありません。
ですが、建築物を適正な状態で維持し続けるには報告書類を保存し続けることをおススメします。
まとめ
今回は、特殊建築物定期検査の詳細を紹介しました。
特殊建築物定期検査の報告時期は3年に1回と定められていますが、各自治体によって報告年度は変わってきます。
また、報告が必要な条件や回数も違ってくるので、各自治体での確認が必要です。
平成24年に建築基準法が改正されて以来、調査の方法や調査項目などが強化されましたが、災害や事故から建物を守るための大切な検査報告なので、きめられた期間にきちんと調査しましょう。
特殊建築物の防火設備定期報告の詳細と報告方法
特殊建築物定期調査とは別に、新たに新設された防火設備定期検査は、建物を火事から守るための大切な定期調査です。
今回は、防火設備定期調査に関する詳細を紹介します。
特殊建築物の防火設備定期報告制度の内容
防火設備検査は、2016年の建築基準法改正によって新たに新設された調査項目です。
特殊建築物(特定建築物)として指定された建築物の防火設備に重点を置いた検査で、病院や診療所などの主に公共性の高い建物が該当します。
建築物の定期報告には防火設備定期報告の他に、特殊建築物定期調査報告など様々な調査報告があります。
特殊建築物定期調査報告の中にも防火設備に関する調査報告をしなければいけない項目がありますが、各定期報告によって調査の仕方、調査報告内容が異なっているので、特殊建築物に設置されている防火設備によって防火設備点検定期報告が必要か必要でないかは変わってきます。
定期調査報告制度の改正前は特殊建築物等定期調査報告の中に含まれている「防火設備の設置状況の確認」の項目にそって報告するだけでしたが、基準が緩く、火災時に防火設備がきちんと作動しなかった事故が多く起きたために、詳しく防火設備を点検するために改正後には特殊建築物等定期調査と別に防火設備定期調査が加えられました。
防火設備の定期報告が必要になる対象と消防用設備等点検との違い
防火設備点検が必要になる条件は、調査対象の建物が特殊建築物であることと煙と熱を感知して動作する防火設備があることの2点です。
防火設備点検の対象となる建築物は特殊建築物と呼ばれる劇場や百貨店、ホテル、病院、販売店、体育館、ボーリング場、映画館、共同住宅、事務所などの個人や家族を含め、その他大勢の不特定多数が利用する公共性の高い建物になります。
また、各自治体によっても追加で指定されている建築物があるので、注意が必要です。
防火設備定期調査の対象となる設備は、建築基準法第12条第3項の規定により「火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備」とされています。
この、「火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備」には、主に屋内の面積や防犯区画ごとに延焼防止目的で設置された火災時の避難経路となる臨時閉鎖式防火設備のことを差します。
避難経路となる防火設備には、防火設備用感知器、自動防火扉、手動防火扉、自動防火シャッター、手動防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー、温度ヒューズ式の防火設備等が該当します。
常に閉まっている通常閉鎖式の防火設備や防火ダンパーは防火設備定期調査報告の対象にはなりません。
また、野外や外部に設置されている扉やシャッターは「防犯設備」に該当するので、防火設備定期調査報告の対象にはなりません。
防火設備点検と消防用設備等点検との違いは、火事を防ぐのか知らせるのかの違いです。
消防用設備に該当するのは、自動火炎報知器、複合型の消火設備、発信機、非常灯、地区音響装置が該当します。
どれも、火事が起きたことを知らせるための装置で、防火設備点検に該当する防火のための装置とは役割が異なります。
防火設備の定期報告の調査方法と必要な書類と資格
防火設備定期調査の主な方法は、防火シャッター、防火扉、耐火クロススクリーンなどの駆動装置の稼働確認と、煙熱感知器との連動閉鎖確認、その他危害防止機能の稼働確認です。
特殊建築物の防火設備定期調査は、原則として1年に1回の頻度で調査する必要があり、専門の資格を所持した調査員が調査を行い地方自治体(特定行政庁)に報告します。
防火設備定期調査をすることができる防火設備調査員になるには、1級建築士又は2級建築士、防火設備検査員の国家資格を習得する必要があります。
防火設備定期調査を報告するために必要な書類は、建築物の所在地がある各地方自治体(特定行政庁)のホームページからダウンロードすることができます。
どの地方自治体のホームページでも、検査項目と検査方法の詳細や必要な提出物、作成方法などが詳しく搭載されています。
特殊建築物の防火設備定期調査に必要な書類は、地方自治体によって多少異なりますが、防火設備定期調査報告書2部と防火設備定期調査報告概要、提出リスト、事務手数料を事前振り込みいた際の振り込み書の写しが必要となります。
防火設備の定期報告を提出する方法
提出先は各都道府県によって、地方自治体か業務を委託された一般財団法人かに分かれるので、事前に確認しておきましょう。
できあがった検査報告書は直接自治体に持参するのではなく、郵送で指定の住所に送ることで報告は完了します。
地方自治体によって異なりますが、直接窓口に持参しても受け取ってもらえない地方自治体が多いので注意が必要です。
提出前に、事務手数料を指定の口座に振り込んでく必要があるので、事務手数料を事前に振り込み、振り込みが確認できる写しを提出書と一緒に同封して郵送するようにしましょう。
まとめ
今回は特殊建築物の防火設備定期調査について紹介しました。
防火設備は火事の際に建物を守る大切な設備なので、きちんと毎年調査し、報告する義務があります。
できあがった検査報告書は直接自治体に持参するのではなく、郵送で指定の住所に送ることで完了します。
特殊建築物調査に比べると調査項目は少ないので、比較的簡単に自身で資格を習得して報告することが可能です。