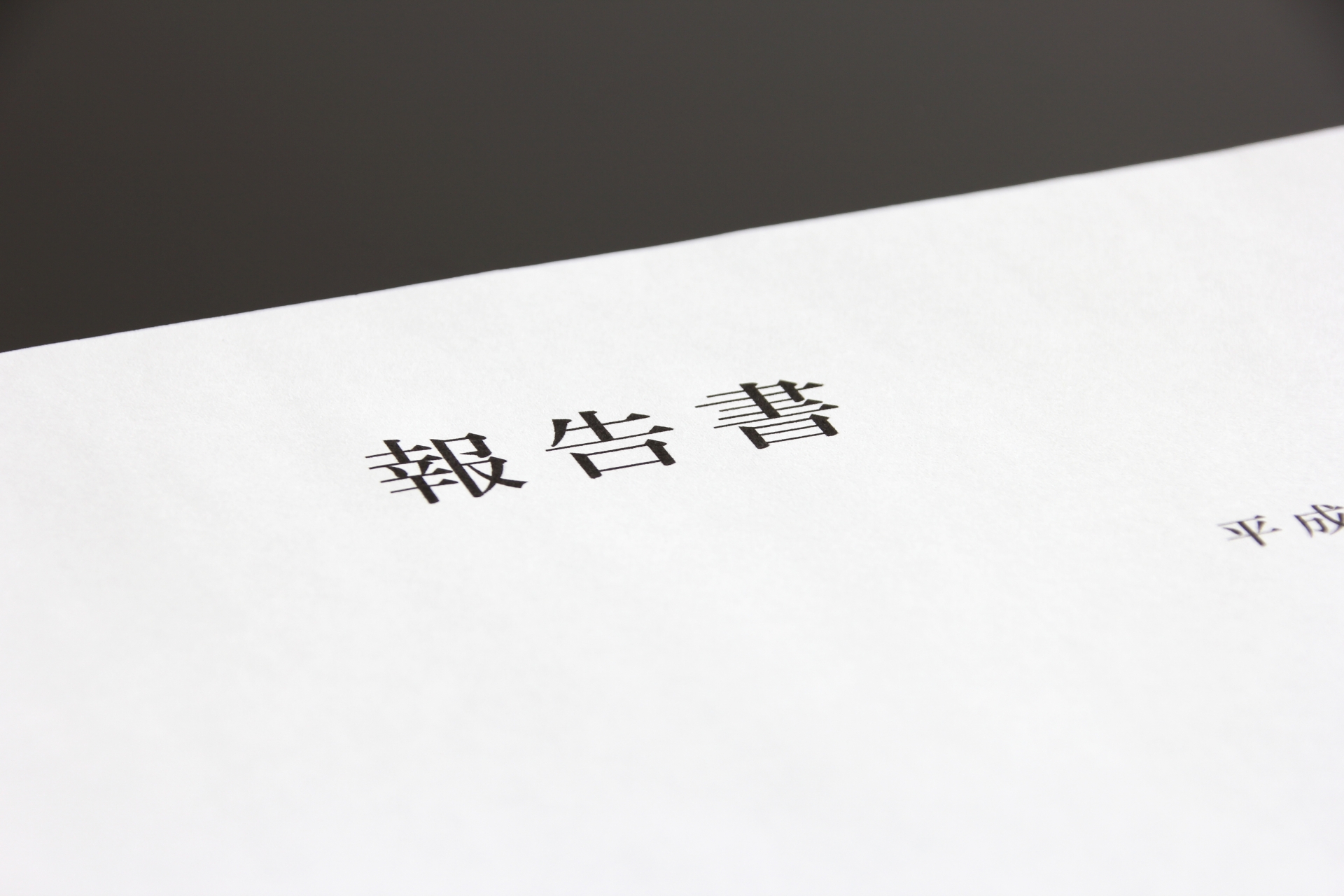兵庫県の防火設備定期報告制度について
最初に定期報告制度についての趣旨・目的を説明します。
建築物が立ち、長い年月利用していく間に物理的な劣化や補修・改修・部品交換などが必要になると思います。
また、災害や事故などやむを得ない理由で劣化してしまう事があります。
このような事に対応出来る様に、専門家による定期的な調査が必要になります。
これが多数の人々が利用する規模の建築物については、被害の拡大も考えられますし、第三者に危害を及ぼすおそれがあると考え、定期の調査を行い、特定行政庁に報告することを義務付けて安全性の確保を図っています。
その中で、毎年建築基準法に基づき、防火設備に対する調査報告が必要となります。
また平成30年度から建築基準法の法改正に伴い、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員による定期調査報告が必要となります。
定期調査には大きく「特定建築物の定期調査」、「建築設備の定期調査」、「防火設備の定期調査」、「昇降機等の定期調査」の4種類があります。
調査の時期は、兵庫県内の各特定行政庁とも、特定建築物については3年に1回、建築設備・防火設備については毎年1回と定めています。
兵庫県の特定行政庁について
兵庫県内の特定行政庁は、兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市、加古川市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、芦屋市、高砂市となります。この中で県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。
神戸市を除く特定行政庁は公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターが定期報告業務の委託先として提出窓口となり、神戸市は市が提出窓口となります。
防火設備調査について
2016年6月から建築基準法が改正された事により新設された検査方法となります。特定建築物として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。
調査対象となる建築物は、防火扉・防火・防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを設置されている建築物です。
建築物の所在地を管轄する特定行政庁によっては指定する条件に細かな差異がある為、より詳しく知りたい場合は、特定行政庁の建築指導課に直接問い合わせるか、定期調査業務を委託する調査者に相談してください。
調査内容について
下記それぞれの防火設備により調査方法が異なりますが、建築基準法112条で規定される防火区画について設計図をみながら確認します。
1.防火扉
防火扉の作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
2.防火シャッター
防火シャッターの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
3.耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、機動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
4.ドレンチャー等
作動状態の確認、各部分の劣化・損傷の確認、加圧送水装置の状態確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
定期調査の報告までの流れ
定期報告書の受付・審査・指導の流れについて下記のとおり説明します。
※注意:報告対象年度には特定行政庁(兵庫県建築防災センター)より通知します。
所有者又は管理者 ⇒定期報告書送付 ⇒兵庫県建築防災センター
⇒通知 ⇒各特定行政庁(審査・指導) ⇒審査結果送付
⇒所有者又は管理者
是正すべき事項がある場合は、所有者又は管理者はその内容を専門技術者と相談し、改善に努めていただく事となります。
指示がある場合は、改善計画書・改善報告書を提出する事となります。
まとめ
繰り返しになりますが、防火設備定期調査は、有資格者である、「一級建築士」、「二級建築士」、「防火設備検査員」が行う事となっています。
「一級建築士」は国家試験に合格し、国土交通大臣より免許を受ける事となっています。「二級建築士」は都道府県知事より免許を受ける事となっています。防火設備検査員は資格を満たしているものが講習を修了し、交付を受ける事となっています。
平成28年以降、虚偽の報告に対して、罰則規定も設けられ建物の安全を守る為に定期調査に対して厳格な対応を行うようになってきました。
防火設備、定期調査の内容を正しく理解し、正しい運用を行うように努めていただければと思います。
兵庫県建築防災センターにおける定期調査報告概要と手数料
兵庫県建築防災センターでの定期調査報告時に必要な手数料について、特殊建築物の定期調査報告の概要と流れを押さえた上で、詳しくご紹介します。
特殊建築物の定期調査概要と報告の流れ
a)概要
建築基準法第8条第1項により、建築物の所有者管理者又は占有者は、その建築物の敷地や構造、建築設備を、常に適法な状態に維持するよう努めなければならないと規定されています。また、不特定多数の人々が利用する大規模な建築物に関しては、万が一、事故や災害が発生した時に多大な被害をもたらす恐れがあります。そのため、建築物の所有者や管理者が、有資格者によって定期調査を行い、特定行政庁に報告することが義務付けられました。この定期報告制度は、建築基準法第12条第1項及び第3項に定められています。
兵庫県の定期報告制度における報告内容は、以下の4種類です。
1 特定建築物の定期調査、報告
2 建築設備の定期検査、報告
3 防火設備の定期検査、報告
4 昇降機等の定期検査、報告
報告対象となる主な建築物や建築設備は、以下の通りです。(いずれも面積による基準あり)
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場
・病院、診療所、児童福祉施設等
・ホテル、旅館
・下宿、共同住宅、寄宿舎
・共同住宅、寄宿舎のうち、サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム障害者グループホームに限る建築物
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
・事務所その他これに類するもの(地下3階以上)
防火設備の定期点検報告について
平成30年度より、一級建築士や二級建築士等の有資格者による毎年の検査報告が義務となりました。対象設備は、随時閉鎖式の防火設備です。(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)
ブロック塀等の定期報告について
組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等も、耐震面から定期報告の対象項目となっています。特殊建築物に付随するこれらの塀に劣化や損傷がないか点検し、安全管理に努める必要があります。
b)定期調査の報告の流れ
兵庫県での定期報告の流れは、まず所有者又は管理者に、定期報告書が送付されます。報告書は、兵庫県建築防災センターが受付し、各々の特定行政庁が審査と指導を行います。審査結果は、所有者又は管理者に送付されます。審査結果に訂正事項がある場合は、特定建築物の所有者又は管理者は、専門技術者とともに改善に努める義務があります。指示のある場合は、改善計画書や改善報告書を提出する場合があります。定期調査報告は3年ごとに行い、建築物の種類によって報告時期が異なります。
なお、兵庫県の特定行政庁は、神戸市・尼崎市・姫路市・西宮市・伊丹市・明石市・加古川市・宝塚市・川西市・三田市・芦屋市・高砂市です。(その他市町村は、兵庫県が地域実態を考慮して指定)
兵庫県建築防災センターにおける定期調査報告の手数料
a)調査費用
定期報告の調査費用は、点検を担当する有資格者の属する設計事務所や調査会社によって異なります。調査範囲や建築物の状況(面積や築年数による劣化・改修状況等)、調査結果報告書の作成範囲、提出代行の有無といった条件でも変わってきます。物件数や調査・報告の時期によって割引をする調査会社もあります。調査依頼前に見積もりを取るのが望ましいと言えます。
b)報告窓口での手数料
定期調査報告の提出時に、兵庫県建築防災センターの窓口では「指導手数料」が必要となります。
調査・検査対象面積又は規模による定期報告等指導手数料(税込)
1 特定建築物
・1,000㎡以内 5,000円
・1,000㎡超〜3,000㎡以内 6,000円
・3,000㎡超〜5,000㎡以内 8,000円
・5,000㎡超〜10,000㎡以内 10,000円
・10,000㎡超〜20,000㎡以内 13,000円
・20,000㎡超〜40,000㎡以内 16,000円
・40,000㎡超 21,000円
2 建築設備3設備(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置) のうち
・1設備 3,000円
・2設備 5,000円
・3設備 6,000円
3 防火設備 4,000円
定期報告を郵送で提出する場合は、指定の下記口座に振込の上、振込書控えのコピーと報告書を一緒に郵送又はFAXします。
三井住友銀行
三宮支店 普通 3850200
公益財団法人 兵庫県住宅建築総合センター
c)その他に掛かる費用
上記の調査費用と窓口での手数料の他に、現地調査や打合せ・報告書提出時の交通費、資料印刷費用等の諸経費が必要となります。
まとめ
特殊建築物の定期調査報告は、調査の前後や報告書の提出時に、さまざまな費用が発生します。事前に調査費用の見積もりを取り、兵庫県建築防災センター窓口で掛かる手数料や諸費用も確認の上、定期調査報告に臨みましょう。
特殊建築物の定期調査 概要と自治体別の報告書書式について
多くの人々が利用する特殊建築物は、適切な維持管理を目的として、定期調査報告が義務付けられています。定期調査の概要をふまえた上で、自治体別に異なる定期報告の書式を説明します。
特殊建築物の定期調査概要と報告方法
a)概要
特殊建築物とは、不特定多数の人々が利用する比較的面積も大きな建築物です。具体的には学校や劇場、百貨店、ホテル・旅館、マンションや飲食店、ダンスホール・ナイトクラブなどです。これらの建築物は、構造や設備が特殊なため、火災や事故が発生した場合に、多くの人々や周辺環境に大きな被害を及ぼす恐れがあります。建築基準法により、特殊建築物は、完成後も建物や設備の適切な維持管理を行い、定期的な点検と報告をすることが義務付けられています。
定期調査では、建築物が損傷や劣化をしていないか、違反の改変がないか等を点検します。建築基準法に基づく定期報告の調査項目は、下記の通りです。
1 建築物(敷地及び地盤・建築物の内部と外部・屋上と屋根・避難施設等)
2 建築設備(換気設備・ 排煙設備・非常用の照明装置・給水設備及び排水設備)
3 昇降機等(エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機・遊戯施設等)
4 防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)
定期調査は、一級建築士・二級建築士、特定建築物調査員などの有資格者が行います。 定期報告をするのは、建築物の所有者または管理者に義務があります。
b)定期調査の報告方法
定期報告の提出は、建築基準法により、特定行政庁に提出することになっています。特定行政庁とは、人口25万人以上で建築主事を設置する自治体のことを言います。人口25万人未満の市区町村では、所属する都道府県が管轄の特定行政庁となります。実際に報告書を提出する窓口は、都道府県や市のホームページで確認できます。
特殊建築物の定期調査 自治体別の書式詳細
a) 兵庫県
兵庫県住宅建築総合センターのページからダウンロードすることができます。兵庫県ホームページからもリンクしています。概要は以下の通りです。
1 特殊建築物定期検査報告書
・報告書
・調査結果表
・調査結果図
・関係写真
2 建築設備定期検査報告書
・報告書
・検査結果表
・測定表
・調査結果図
・関係写真
・国土交通大臣が定める項目の検査計画書
3 防火設備定期検査報告書
・報告書
・検査結果表
・調査結果図
・関係写真
4 添付図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
いずれもA4(折り・縮小版可)
指摘のあった箇所や、防火区画がある場合は、図面上に赤書き等で明示する
b) 神戸市
神戸市ホームページ「定期報告制度(建築物・建築設備・防火設備)」ページからダウンロードできます。概要は以下の通りです。
1 報告書表紙
2 特殊建築物等の定期調査報告書の報告内容について
3 定期調査報告書 第1面から第4面
4 階別用途別床面積不要の場合は省略可能
5 建築物の履歴に関する事項
6 調査結果表
7 図面等(付近見取り図:A3折り図またはA4)
イ.付近見取図:A3折図又はA4図
ロ.配置図:原則A3折図(容易に判別できる場合はA4縮小可)
ハ.各階平面図:上記同じ
・防火区画(赤線)、防火設備の種別、防煙区画(青線)を明示する
・避難経路(赤点線)を明示する
・指摘のあった箇所や撮影した写真の位置を明記する
二.関係写真:A4
8 定期調査報告概要書
c) 大阪市
大阪建築防災センターのサイトより、書式をダウンロードできます。概要は以下の通りです。
1 報告書(第一面〜第三面)
2 建築物定期調査結果書
3 調査結果表
4 調査結果図(配置図・各階平面図)
5 関係写真
6 概要書
d) 京都府
京都府ホームページ「特定建築物等の定期報告制度について」ページからダウンロードできます。概要は以下の通りです。
1 定期調査報告書
2 定期調査概要書
3 調査結果表
4 調査結果図
5 関係写真
6 添付図面
・付近見取図(方位、道路及び目標となる地物)
・配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置・用途、敷地に接する道路の位置・幅員)
・建築物の各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置、開口部・防火戸の位置、延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏の構造、防火区画・隔壁の位置、非常口、非常用進入口・避難施設の位置)
まとめ
定期報告の書式は、特定行政庁や都道府県・市によって異なります。建築物の所在地を管轄する自治体の情報を確認して、指定の書式を使用しましょう。また、報告書には図面等の添付書類が必要です。書類をもれなく揃えて、指示通りの記入をして提出する必要があります。特殊建築物は多くの人々が利用する建物です。長く安全に維持管理ができるよう、定期報告を適切に行うことが重要です。
特定建築物定期調査の外壁全面打診 調査対象や調査方法について
特殊建築物の定期調査報告において、外壁面の調査基準が厳しくなりました。全面打診調査の対象となる建築物の条件や、調査方法、費用について詳しく見ていきましょう。
特定建築物定期調査の外壁全面打診詳細 調査対象と範囲・方法
外壁全面打診調査は、エレベーター・ジェットコースターの事故や外壁の落下事故が多く発生したことを受けて、平成20年に国土交通省により施行されました。従来の定期報告制度の検査項目や方法を、より厳しく変更した内容です。法改正前は、定期報告時の目視と部分的な打診調査を行い、異常判明時には精密検査を要する旨の注意喚起を行っていました。法改正後は、外壁面が指定の条件に該当する場合、全面打診調査が必要となりました。
a)調査対象となる外装仕上げ材
調査対象となる外装仕上げ材は、主に以下の3種類です。
・タイル貼り(接着剤張り・ 適用下地・施工記録あり) ※全面改修を含む )
・石貼り(乾式工法を除く)
・モルタル貼り
b)全面打診調査が必要な範囲
建築基準法第12条に基づき、全面打診調査と定期報告の対象となるのは、建築物の竣工後または外壁の改修後、10年を超えた物件です。調査は、主に外壁の損傷確認や剥落防止、歩行者等への危害防止と補修・落下防止方法の検討のために実施されます。
10年以内の竣工・改修物件や、外装材にタイル・石貼り・モルタル貼りを使用していない物件は、目視による調査を実施します。10年超の物件でも、3年以内に外壁改修または全面打診調査を行うことが確実である場合や、歩行者の安全対策が取られている場合は、目視及び手の届く範囲内での部分打診調査を実施します。ただし、目視や部分打診調査で以上が判明した場合は、全面打診調査が必要となります。
全面打診調査が必要となる範囲は「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」です。これは、当該壁面の前面かつ当該壁面高さ概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内道路、広場を有する物のことです。
壁面直下に、鉄筋コンクリートや鉄骨で造られた、落下物から歩行者を守る設備がある場合や、屋根や庇、植込等の設置により、落下物の影響角が完全に遮られる部分がある場合は、調査対象外となります。
c)全面打診調査の調査方法
テストハンマーなど専用の道具で全面を打診する調査、又は赤外線調査を行います。
・打診調査
対象建築物が低層なのか高層なのかによって、全面打診調査の方法は異なります。1階から3階建の低層建築物の場合は、脚立やアップスライダーを利用して調査できます。4階建以上の中高層建築物は、ゴンドラや高所作業車の利用、屋上からロープを下げる、仮設足場を設置するといった方法が必要になり、調査費用の負担が大きくなります。
高所作業車は高層建築物の打診調査にも利用できますが、作業車を設置する敷地のスペースや、公道にかかる場合は道路使用許可や交通整理人員等が必要となってきます。
打診調査は、 外壁の落下で歩行者に危害を加える恐れがある部分の外壁全面に対して行います。タイルやモルタルに浮きがある場合、打音の変化が生じるため、浮きの場所と程度が判定できます。調査担当者の経験値により、多様な打音の聴き分けや測定時間の短縮につながります。聴力による判定のため、測定時間をより短くすることが調査精度を高めます。
・赤外線調査
赤外線調査は、赤外線の映像装置でタイルの表面温度を測定することで、正常な部分(健全部)と、浮きのある異常部分を判定します。 外壁タイルの健全部は、太陽光の熱で温まると、その熱が躯体に伝わります。外壁タイルに浮きがある場合は、躯体と仕上げ材に空気の隙間ができ、熱が伝わりにくくなるため、外装表面温度が高くなります。
赤外線調査のメリットは、打診調査より比較的安価で安全なことと、現地調査から報告書の提出までが素早く完了できることです。調査時に打診音がないため、建物の居住者の負担が少ないことも安心です。
赤外線調査は測定環境の影響を受けます。天候や外壁面の方角、凹凸、測定機材の使用方法によっ、て精度が下がる場合があります。測定機材と外壁の間に障害物があると、正しい測定の妨げとなります。高層部でも赤外線測定は困難です。
d)費用
外壁調査の費用は、調査する外壁面の面積と、調査方法によって異なります。
打診調査の場合、ゴンドラ利用やロープ降下等、状況により見積もりを取って確認する必要があります。高所作業車の使用や、仮設足場を組む必要がある場合は、費用が高額になります。その他にも、打診費用と報告書(損傷図等)の作成費用がかかります。
赤外線調査は、高所作業車や足場設置の費用に比べて、コストが抑えられる傾向にあります。目視と部分写真を含む赤外線の撮影と、画像の解析費用、報告書の作成費用(写真台帳・損傷図等)がかかります。
まとめ
歩行者の安全を守るために、外装材の全面打診調査と適切な補修が必要です。建築物の条件により、調査方法や費用は異なります。まずは対象の外装材がどうか、全面調査にかかる費用の見積もりを確認し、法令で義務付けられた定期調査と報告・改善を実施しましょう。
特殊建築物の定期調査報告を怠るとどうなる?規定と罰則
特殊建築物には定期調査報告制度があり、一定の時期に報告をすることが決められています。ではこの定期調査や報告を怠ったり、偽ったりした場合、どのような罰則処分があるのでしょうか。過去の具体的な事例とともに見ていきましょう。
特殊建築物の定期調査報告に関する罰則はどのようなものか
a)法律的な表記
建築基準法第101条に罰則規定が記載されています。
第7章 罰則 第101条(抜粋)
「次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。二 第12条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者」
b)特定行政庁による立入検査
特定行政庁は、建築物の維持管理が適切になされていない場合や、定期報告の督促を行っても応じない場合に、立入検査と指導を行うことがあります。それでも改善が見られない場合に、罰則が適用されることがあります。
立入検査の実施例として、平成24年5月に起きた広島県のプリンスホテル火災事故の後には、全国のホテル・旅館で、平成27年5月に起きた神奈川県の簡易宿泊所の火災事故の後には全国の簡易宿泊所等で、立入検査が行われました。
特定行政庁とは、建築主事の設置された都道府県や市のことを指します。建築主事は人口25万人以上の自治体に設置されるため、人口25万人未満の市区町村では、建築主事に代わり、都道府県が管轄の特定行政庁となります。特定建築物の定期報告は、その建築物の管轄の特定行政庁に報告書を提出します。
定期報告の時期は、特殊建築物は3年に1回、昇降機と建築設備の定期調査の報告は年1回となっています。新築の建築物の場合には、検査済証の交付直後は報告の必要がありません。
c)罰則内容、基準等
定期報告制度は、建築基準法第12条で定められています。
定期報告の提出を怠ったり、虚偽報告をした場合は、100万円以下の罰金処分となる可能性があります。定期報告通知を無視して、報告書の提出期限を過ぎた場合には、督促状が送付されます。
定期調査を実施する有資格者も、罰則処分の対象となります。虚偽の報告をした場合、資格者証の返納が命じられます。返納に応じない場合、30万円以下の罰金処分となります。報告の義務を怠って火災事故が発生し、防災設備の状況や避難の対策がずさんで悪質と判断された場合、執行猶予のつかない実刑判決になった事例もあります。
特殊建築物の事故や災害による甚大な被害を防ぐため、国土交通省と特定行政庁は、定期報告制度の順守を推進し、建築物が安全に維持管理されるよう力を入れています。
d)建物の管理者責任について
建築物の所有者又は管理者が、定期調査や適切な維持管理を怠り他人に損害を生じたときは、その損害を賠償しなければなりません。
建築物や設備の点検は、その設備の所有者の管理を超えて、一級建築士や二級建築士など有資格者による定期的な点検調査が行われます。そして特定行政庁に調査の報告をすることが義務付けられています。
特殊建築物の所有者又は管理者は日頃から安全管理に努め、どのような事情があっても、定めに従って建築物と防災設備の点検を実施し、定期調査報告後に指摘があった場合は、専門技術者と相談の上、速やかに改善を図ることが求められます。
定期調査報告を怠り罰則処分となった具体的な事例
a)事例1
ホテルプリンス火災事故(平成24年5月 広島県福山市)
火災により宿泊客7名が死亡し、従業員1名を含む4名が重傷を負いました。ホテルの社長は業務上過失致死傷害罪に問われ、執行猶予5年、禁固3年の有罪判決となりました。
調査によると、排煙設備の未設置により、煙が充満し視界が悪くなり逃げ遅れたこと、 内装に使われているベニヤ板が救助活動の妨げとなったことなどが被害を大きくしたと見られています。排煙設備の設置は、法律で義務付けられているものでした。また、防火設備の定期報告が38年間行われなかったなど、危機管理のずさんさも問われました。
b)事例2
歌舞伎町ビル火災事故(平成13年9月 東京都新宿区)
雑居ビルの火災により、3階と4階にいた44名が死亡し、脱出時の負傷者も出ました。
自動火災報知器は、誤作動が多いことを理由に電源が切られており、4階は火災報知機を含めた天井部分が、内装材で覆い隠されていました。定期調査報告を怠ったため、避難器具の未設置や正常に作動しないなど、状況が改善されなかった例です。ビルは火災後に使用禁止命令が下され、その後遺族との和解が成立しましたが、ビルは解体されました。和解金は総額10億円を超えると言われました。ビルの管理者5名は、執行猶予付の有罪判決となりました。
まとめ
定期調査報告の目的は、万が一に備え、人命を救い被害を最小限に抑えることです。 正しく定期調査と報告をしていれば、建築物の防災設備の不備や火災発生時の避難経路の問題など、事前に危険を察知し、状況の改善が望めます。定期調査を怠り、報告をしない又は虚偽の報告をすることによって、事故発生時の被害が大きくなった場合には、取り返しのつかない事態となり、罰則も適用されることになります。
特殊建築物の防火設備の定期調査とは?点検内容と対象設備
特殊建築物の防火設備は、定期的な調査と報告が義務付けられています。法律で定められた点検内容には、どのような項目があるのか、また、点検の対象となる防火設備について具体的にご説明します。
防火設備の定期調査には建築基準法と消防法の点検がある
a)概要
平成28年度建築基準法の改正に伴い、防火設備の定期調査についても制度が改正されました。この背景には、平成25年10月に福岡県の診療所で発生した火災事故があります。火災発生時に自動的に閉まるはずの防火扉が作動せず、多数の犠牲者が出る痛ましい事故となりました。このような事故の再発防止のために、防火設備は定期調査が強化されました。
点検調査を行う資格があるのは、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防災設備検査員のいずれかの有資格者となります。報告書は、各都道府県の決まった様式で提出することになります。
定期報告の対象建築物は、不特定多数の者が利用する建築物とその防火設備、高齢者や自力避難が困難な物が就寝する施設とその防火設備、エレベーターやエスカレーターなどです。
具体的には下記のような建築物で、床面積や階層が規定の数値を超えるものが対象となります。
・劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂又は集会場
・病院、診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設
・体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
防火設備の定期調査は、毎年1回の報告が定められています。これは、火災発生時に防火設備が正常に作動しないと、人命に関わる大きな影響を及ぼすためです。平成28年から30年度までの3年間は経過措置として、1回目の報告実施と決められています。
b)建築基準法の点検内容
防火設備の定期調査は、建築基準法の定めと消防法の定めの2種類があります。
建築基準法では、煙感知器や熱感知器、ヒューズ装置、防火扉と防火シャッター、耐火クロススクリーンの点検が定められています。
建築基準法における防火設備の点検は、延焼防止のための防火区画を形成することで、火災発生時に安全に避難できる経路を確保することを目的として、設備が正常に作動するかを確認します。
c)消防法の点検内容
これに対して、消防法では、煙感知器と熱感知器、火災報知機と室内の火災設備や消火器の点検が定められています。
建築基準法と消防法の両方に共通するのは、連動制御器の点検です。
消防法による消防設備の点検は、火災発生を知らせる警報や消火設備が正常に作動するかどうかの点検です。
消防法による点検が設備の正常作動を主としているのに対して、建築基準法における防火設備の定期調査は、人命の安全が最終的な目的となっています。
特殊建築物の定期調査対象となる4つの防火設備
a)防火扉
主に屋内に、延焼防止の目的で設置され、火災発生時には避難経路となります。防火設備の定期調査の対象となるのは、随時閉鎖式の防火扉です。随時閉鎖式の防火扉は、通常解放されており、火災発生時に感知器と連動して閉鎖されるものです。 火災発生時に防火扉が正常に閉まるか点検が行われます。また、扉の閉まり方が強く早いと、人が挟まれて怪我をする危険があるため、防火扉も締まり方について測定が行われます。
一方、常時閉鎖式の防火扉は、普段は閉まっており、通行するときのみ開閉します。こちらは防火設備の定期検査対象外となり、特定建築物の調査対象となります。
b)防火シャッター
防火シャッターは、主に屋内で建物の開口部が大きく、その開口部を閉鎖する必要がある場合、延焼を防止する目的で設置されます。百貨店やショッピングモール、病院施設など、主に大型建築物や複合施設によく見られます。防火シャッターは必要な時だけ閉めるため、常時閉鎖式にはなりません。火災感知器や非常ボタンでシャッターが閉まります。 定期調査の内容として、シャッターの開閉や感知器との連動、シャッターボックスの破損などがないかを点検します。防火シャッターは、シャッターが閉まった際に人が挟まれて怪我をしないよう、危害防止装置のついたものがあります。この装置が正しく動作するかも点検対象です。
c)耐火クロススクリーン
防火シャッターと同様に、屋内で延焼防止のために設置される、天井から閉め降ろすタイプの防火設備です。エレベーターの前や倉庫などで見られ、耐火クロススクリーンの素材はガラス製のクロスです。防火シャッターより耐火クロススクリーンが軽量でペン素材も柔らかいため、人が挟まれる危険性が少ないのが特徴です。
耐火クロススクリーンの点検項目は、感知器との連動と正常に閉まるかどうか、巻取式で開閉するクロスクリーンの場合は、危害防止装置が正常に作動するかも確認します。
d)ドレンチャー
ドレンチャーは、火災発生時に天井部から水が噴射され、水の膜を作って炎や煙が拡がるのを防ぎます。駅や空港など、防火シャッターや耐火クロスクリーンでは対応できない大きな空間に用いられます。
ドレンチャーは、点検であっても実際に水の噴射を作動させることができないため、専門の技術者によって点検が行われます。
以上4種類の防火設備について、定期調査報告では、平面図に対象防火設備の設置箇所を記入し、所有者・管理者の情報や対象建築物の報告書とともに提出します。
まとめ
防火設備は、いざという時に多数の人命を守る重要な役割を担います。多くの人々が利用する大型施設に使用されることも多いため、定期調査により不具合や消耗を発見し改善することは必須です。火災事故を未然に防ぎ、万が一の場合も被害を最小限に抑えることにつながります。
兵庫県の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
特殊建築物は定期調査と報告が定められていますが、その管轄や定期報告の提出先は自治体によって異なります。兵庫県の場合、定期報告制度はどのような内容なのか、報告対象の建築物や報告方法を具体的に見ていきましょう。
兵庫県の特殊建築物の定期調査 概要と報告対象について
a)概要
建築基準法第8条第1項により、建築物の所有者管理者又は占有者は、その建築物の敷地や構造、建築設備を、常に適法な状態に維持するよう努めなければならないと規定されています。また、不特定多数の人々が利用する大規模な建築物に関しては、万が一、事故や災害が発生した時に多大な被害をもたらす恐れがあります。そのため、建築物の所有者や管理者が、有資格者によって定期調査を行い、特定行政庁に報告することが義務付けられました。この定期報告制度は、建築基準法第12条第1項及び第3項に定められています。
兵庫県での定期報告の流れは、まず所有者又は管理者に、定期報告書が送付されます。報告書は、兵庫県建築防災センターが受付し、各々の特定行政庁が審査と指導を行います。審査結果は、所有者又は管理者に送付されます。 審査結果に訂正事項がある場合は、特定建築物の所有者又は管理者は、専門技術者とともに改善に努める義務があります。指示のある場合は、改善計画書や改善報告書を提出する場合があります。
b)兵庫県内の特定行政庁
定期報告の対象建築物等は、国の政令による指定の他に特定行政庁、特定行政庁以外の市町区域は、兵庫県が地域の実態を考慮して指定しています。
兵庫県の特定行政庁は、以下の12市です。
神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市
c)報告対象となる建築物・建築設備
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(200㎡以上)
・病院、診療所、児童福祉施設等(300㎡以上)
・ホテル、旅館(300㎡以上)
・下宿、共同住宅、寄宿舎(100㎡以上)
・共同住宅、寄宿舎のうち、サービス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム障害者グループホームに限る建築物(300㎡以上)
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(2000㎡以上)
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(500㎡以上)
・事務所その他これに類するもの(地下3階以上)
兵庫県が特定行政庁として管轄する市町区域では、定期報告の業務を行う有資格者等が、対象となる特殊建築物のリストを閲覧することができます。これは定期報告の実施率を向上させる目的で提供されています。
防火設備の定期点検報告について
平成30年度より、一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員の有資格者による、毎年の検査報告が義務となりました。
対象となる防火設備は、随時閉鎖式(普段開いていて、火災発生時に煙や熱の感知により作動して閉まる)防火設備です。
防火設備は、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーです。
常時閉鎖式の防火設備(普段閉まっており、火災発生時に開ける防火設備)、外壁開口部設置の防火設備や防火ダンパーは、定期点検報告の対象外となります。
ブロック塀等の定期報告について
組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等も、耐震の面から定期報告の対象項目となっています。特殊建築物に付随するこれらの塀に劣化や損傷がないか点検し、安全管理に努める必要があります。
d)報告する内容
兵庫県の定期報告制度には、下記の4種類の報告内容があります。
・特定建築物の定期調査、報告
・建築設備の定期検査、報告
・防火設備の定期検査、報告
・昇降機等の定期検査、報告
兵庫県の定期調査報告はどのような流れで行うのか
a)兵庫県の定期報告に関する提出先・管轄
特定行政庁が県の場合は県知事宛、市の場合は市長宛に報告します。神戸市以外の特定行政庁は、定期報告業務の委託先として、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターに報告書を提出することもできます。神戸市は市のみが提出先です。
定期報告に必要な書類の要綱と書式は、インターネット上の兵庫県住宅建築総合センターのページからダウンロードすることができます。
b)報告時期
定期調査報告は3年ごとに行い、建築物の種類によって報告時期が異なります。
・劇場や観覧場、病院診療所は、3年ごと、平成32年7月から10月
・ホテルや旅館、下宿、共同住宅、サービス付き高齢者向け住宅は、3年ごと、平成30年7月から10月
・学校や博物館、百貨店、事務所その他は、3年ごと、平成31年7月から10月です。
まとめ
特定建築物の定期調査は3年ごとに行う必要があります。報告書の提出先は、市町村によって異なります。報告時期も建物の種類によって違うため、確認が必要です。防火設備についても定期調査と報告が定められていますので、こちらもあわせて確認しましょう。
神戸市の特殊建築物の定期調査報告制度 対象建築物や報告方法詳細
特殊建築物は、定期的に調査と報告を行うことが定められています。神戸市の場合、どのような建築物や建築設備が点検・報告対象となるのでしょうか。また、定期報告の提出先や報告書の具体的な仕様について、詳しく見ていきましょう。
神戸市の特殊建築物の定期調査 概要と報告対象について
a)概要
建築基準法第12条第1項で定められた特殊建築物等の定期調査に基づき、特殊建築物の所有者や管理者は、調査の有資格者に定期的に対象建築物を調査してもらい、特定行政庁に報告する必要があります。この特殊建築物等定期報告制度は、建築物の安全管理を目的として、3年に1回、調査と報告を行う制度です。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合には、罰則処分の対象となります。
特殊建築物の定期調査報告書の提出状況は、神戸市のホームページで公表されています。これは、建築物の安全な維持管理の大切さを、広く市民に理解してもらうために行われています。
b)報告対象となる建築物・建築設備
・劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場(建物全体で200㎡以上)
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(建物全体で2,000㎡以上)
・百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場(建物全体で500㎡以上)
・病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グル ープホームに限る)、ホテル、旅館(建物全体で300㎡以上)
・事務所その他これに類するもの(建物全体で 1,000㎡以上)
・共同住宅(建物全体で500㎡以上)
・公衆浴場(建物全体で 3,000㎡以上)
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店(建物全体で500㎡以上)
対象建築物を取り壊したり、現存していない場合や、新築又は全面改築による検査済証の交付直後については、定期調査の報告対象外となります。
建築基準法による特殊建築物の定期報告の他に、指定建築設備、防火設備、昇降機等は別途報告が必要です。これらは対象範囲や報告時期が特殊建築物の場合と異なります。
c)報告済ステッカー
定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者には、定期報告済ステッカーが配布されます。定期調査報告制度の報告率を向上し、制度を広く知ってもらうためにこのステッカーが生まれました。定期調査済の建築物の出入口など、広く皆の目に触れる所にステッカーを貼ることで、定期調査報告制度を推進することを目的としています。
定期調査報告は、神戸市では3年に1回必要となるため、ステッカーの色が青と緑とピンクで分かれており、これらの色によって次回の定期報告の年度が分かるようになっています。
神戸市の特殊建築物の定期調査 概要と報告対象について
a)概要
建築基準法第12条第1項で定められた特殊建築物等の定期調査に基づき、特殊建築物の所有者や管理者は、調査の有資格者に定期的に対象建築物を調査してもらい、特定行政庁に報告する必要があります。この特殊建築物等定期報告制度は、建築物の安全管理を目的として、3年に1回、調査と報告を行う制度です。
定期報告の義務を怠ったり、虚偽報告をした場合には、罰則処分の対象となります。
特殊建築物の定期調査報告書の提出状況は、神戸市のホームページで公表されています。これは、建築物の安全な維持管理の大切さを、広く市民に理解してもらうために行われています。
b)報告対象となる建築物・建築設備
・劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂 、集会場(建物全体で200㎡以上)
・学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場(建物全体で2,000㎡以上)
・百貨店、マーケット、 物品販売業を営む店舗、 展示場(建物全体で500㎡以上)
・病院、診療所、 児童福祉施設等、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グル ープホームに限る)、ホテル、旅館(建物全体で300㎡以上)
・事務所その他これに類するもの(建物全体で 1,000㎡以上)
・共同住宅(建物全体で500㎡以上)
・公衆浴場(建物全体で 3,000㎡以上)
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店(建物全体で500㎡以上)
対象建築物を取り壊したり、現存していない場合や、新築又は全面改築による検査済証の交付直後については、定期調査の報告対象外となります。
建築基準法による特殊建築物の定期報告の他に、指定建築設備、防火設備、昇降機等は別途報告が必要です。これらは対象範囲や報告時期が特殊建築物の場合と異なります。
c)報告済ステッカー
定期調査報告を行った建築物の所有者や管理者には、定期報告済ステッカーが配布されます。定期調査報告制度の報告率を向上し、制度を広く知ってもらうためにこのステッカーが生まれました。定期調査済の建築物の出入口など、広く皆の目に触れる所にステッカーを貼ることで、定期調査報告制度を推進することを目的としています。
定期調査報告は、神戸市では3年に1回必要となるため、ステッカーの色が青と緑とピンクで分かれており、これらの色によって次回の定期報告の年度が分かるようになっています。
神戸市における定期調査報告方法の詳細
a)神戸市の定期報告に関する提出先・管轄
神戸市の定期調査の報告書提出先は、神戸市住宅都市局安全対策課ビル防災対策係です。報告書は、調査をした有資格者が直接提出先に持参することが決められています。郵送や代理提出は認められていません。
b)報告時期
報告時期は平成30年の場合8月1日から11月30日までの4ヶ月間となっており、調査後3ヶ月以内に報告する必要があります。
c)仕様書・様式等
特殊建築物等定期調査報告書は指定の使用形式があります。平成28年度より建築基準法改正に伴って使用する様式となっており、神戸市のホームページからもダウンロードできます。
具体的な様式は以下の通りです。
1 報告書表紙
2 特殊建築物等の定期調査報告書の報告内容について
3 定期調査報告書 第1面から第4面
4 階別用途別床面積不要の場合は省略可能
5 建築物の履歴に関する事項
6 調査結果表
7 図面等(付近見取り図:A3折り図またはA4)
イ.付近見取図:A3折図又はA4図
ロ.配置図:原則A3折図(容易に判別できる場合はA4縮小可)
ハ.各階平面図:上記同じ
・防火区画(赤線)、防火設備の種別、防煙区画(青線)を明示する
・避難経路(赤点線)を明示する
・指摘のあった箇所や撮影した写真の位置を明記する
二.関係写真:A4
2 定期調査報告概要書 1部提出
是正項目があった場合は、改善箇所や是正方法、改善完了までの安全確保について記した改善計画書を提出する必要があります。その後、改善完了時には、改善完了報告書も提出します。
まとめ
同じ兵庫県内でも、市町村によって定期調査の提出先や提出書類の仕様が異なります。神戸市では報告書を神戸市に直接提出することが定められ、報告書の形式も定められた雛形があります。これらを事前に確認した上で、特定建築物の所有者又は管理者は、適切な対応が求められます。
大阪府の特定建築物・特定建築設備の内容や報告方法
各都道府県や地方政府によって特定建築物や特定建築設備の対象や調査内容、報告方式、報告先は変わってきます。この記事では大阪府での特定建築物と特定建築設備の調査内容や報告方式などを詳しく解説します。
大阪府の特定建築物調査・特定建築設備調査の概要や報告率
定期調査の概要は、維持管理・保全の不備や不具合によって時大きな事故や災害が発生したり、被害が拡大することを未然に防ぐ事です。
大阪府では特定建築物、特定建築設備、防火設備の報告が義務付けられており、昇降機等の定期報告は一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会が指示、管理しています。
特定建築物調査と特定建築設備調査は、安全な維持・保全管理と複数の人が安心して建物、施設を利用することができるように、建築基準法によって特定期間ごとに調査と報告が義務つけられています。
調査と報告が義務付けられているにもかかわらず、大阪府の特定建築物調査の報告率は約79%、建築設備調査は約77%となっています。
大きなビルや広大な範囲の地下街、複雑な設備だと毎年報告が必要な特定建築物や特定建築設備の調査が追い付かない場合も多いので、大阪府の報告率は毎年75%から80%ほどのにとどまっています。
故意的に調査、報告を既定の期間内に報告しなかった場合は、建築基準法第101条によって100万円以下の罰金が科せられます。
大阪府で対象となる特定建築物・特定建築設備と調査・報告する内容
大阪府で特定建築物に分類される建物は学校、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、博物館、美術館、図書館、集会場、劇場、ホテル、旅館、病院、診療所、児童福祉施設等、百貨店、物販店舗、飲食店、共同住宅、その他サービス店です。
大阪府が特定する建物は他県と比べるととても幅広く、指定の規模の大きさはさまざまですが、博物館や学校など比較的大きな3階以上2000㎡から3000㎡以上の規模の建物から、個室ビデオ店や劇場など床面積が200㎡からの小さな店舗も特定建築物に指定されます。
特定建築設備に分類される設備は機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備で給排水設備は対象外になっています。
学校やボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場は特定建築設備検査の対象外になります。
大阪府で特定建築物・特定建築設備の報告をするには?
大阪府の特定建築物調査はどの建物もすべて3年に1度の定期調査が必要になります。
特定建築物の報告に必要な書類は受付票、報告書様式、和泉市内の建物は調査結果表も作成する必要があります。
特定建築設備の報告に必要な書類は報告書様式のみです。
報告書は一般社団法人大阪建築防災センターのホームページからダウンロードすることができ、パソコンから記入できるEXCEL用と手書き用の2種類が用意されています。
どの書類にも報告書作成上の注意点・記入方法・つづり方・調査項目・調査方法・判定基準が詳しく書かれたマニュアルも送付されています。
自信が資格取得者である場合は調査を行い指定の報告書様式に調査結果を記入し、特定行政庁に提出することで報告は完了します。
資格がない場合は専門の業者に委託することで調査から報告書の作成まで行ってもらうことができます。
大阪府の定期報告先である特定行政庁は、大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の17か所で、それ以外の市町村は一般社団法人大阪建築防災センターが提出先になります。
報告に関する注意点
調査結果の報告に使用する報告書様式は毎年新しい様式に更新されているので、一度ダウンロードした用紙を毎年流用せずに毎年新しい報告書をダウンロードするようにしましょう。
最新の報告様式でなければ受理してもらうことができません。
大阪府では特定建築物・特定建築設備の提出の際に、建物の規模によって3000円から15000円の支援サービス料が必要になります。
大阪府の特定建築物の調査報告は例年4月1日から12月25日までとなっています。
支援サービス料の早期提出割引を受けるには4月1日から8月末までに報告書を提出する必要があります。
報告期限内に報告がない場合は、翌年の1月下旬から2月中旬ごろに督促状が送付されます。
原則、報告様式は直接窓口に提出する必要があります。
まとめ
大阪府はほとんどの商業施設やサービス施設の建物が特定建築物の定期検査に該当します。
特定建築設備の検査では給排水設備の項目は対象外になります。
大阪府での定期検査報告の際には支援サービス料が提出と同時に必要になります。
一般社団法人大阪建築防災センターの定期検査報告のホームページに、必要事項や調査の仕方など詳しく記載されているので、初めての調査報告でも安心して行うことができます。
特殊建築物の定期調査って何?建築設備との違いは?
特殊建築物検査と建築設備定期検査の目的は、共に建築物の異常に起因する人身的・経済的な事故を事前に防ぐのが目的で建築基準法で調査と報告が義務つけられています。ですが、細かな点で違いがあるので検査しなければいけない建物がどちらに適しているのか分からなくなってしまいます。この記事では特殊建築物検査と建築設備検査の違いについて解説します。
特殊建築物調査って何?何のために必要な調査なの?義務を怠ったら?
特殊建築物調査は建築基準法によって報告が義務つけられており、利用者の安全を常に保証するための法律です。
特殊建築物に特定された公共性の高い建築物は、建物全体が常に適切で適法状態であることを定期的に報告しなければいけません。なぜなら、特殊建築物は通常の戸建てとは違い構造や設備の規模が大きく異なり、小さな劣化や不備でも大きな事故や災害など大惨事になってしまうリスクが高いからです。
建物を使用する利用者のために、外装や内装から避難経路や避難設備、昇降設備などすべての面で基準値を満たしておく必要があります。
特殊建築物調査の調査内容は政命や地方行政、国土交通省によって大まかな項目は同じですが細かな項目は変わってきます。
ですが、必ず定期報告をしなければいけないことには変わりありません。
特定建築物の調査や報告は規模によって1年ごとの報告が必要な建物と、3年に1度の報告で済む建物に分かれます。
どちらの場合でも特殊建築物調査の報告を怠った場合は建築基準法第101条によって100万円以下の罰金が科せられます。また、虚偽の報告をした場合も同じく100万円以下の罰金が科せられます。
特殊建築物の対象は?どんなことを調査されるの?
特殊建築物調査の対象は映画館、宿泊施設、百貨店、マーケット、病院、学校、博物館、美術館、共同住宅などの複数の人が利用する建物で、その建物が政令や行政が定めた土地や建物の規模、階数、構造の条件に当てはまると特殊建築物調査が必要になります。特殊建築物に該当すると、調査の義務と同時に構造や防火設備、昇降設備の条件も厳しくなります。
調査の主な項目は敷地・地盤、建物外部、建物内部、屋根・屋上、避難設備・非常用進入口、その他耐震設備や逃雷設備などになります。
敷地・地盤
堀や壁にひび割れがないか、排水がきちんと行われているか、敷地の通路が適切であるか、地盤に問題がないかを調査されます。
建物外部
広告板や室外機などすべてを目視を中心にひび割れや沈下がないかを確認されます。
建物内部
建築図面と内部を照らし合わせながら目視によって防火区画や壁、床、天井、通路などに異常がないかを調査されます。
屋根・屋上
目視を中心にパラペットやドレーンなどに劣化や破損がないか、排水がきちんと行われているかを確認されます。
避難設備・非常用進入口
建築図面と照らし合わせながら廊下や通路、出入口、バルコニー、階段、非常用進入口に異常や劣化はないか、排煙設備や火災時対策に問題はないかを調査されます。
その他設備
耐震設備や逃雷設備などは目視によって劣化がないかを確認されます。
調査は自分でもできる?報告の方法は?
特定建築物の定期検査は自信で調査し報告書を作成することができます。
ですが、指定の資格保有者でないと調査や報告はできません。
特定建築物の調査が可能な資格は特定建築物調査員、1級建築士、2級建築士です。
1級・2級建築士は特定建築物と同時に建築設備検査、防火設備検査、昇降機等調査を行うことができますが、特殊建築物調査員は特定建築物だけしか調査を行うことができません。
報告に必要な書類は、調査報告書を提出するところで受け取るか、各地方政府や特定行政府のホームページからダウンロードすることが可能です。
ガイドラインに従って必要事項を調査し、記入例に沿って結果を記入することで報告書ができあがります。
建築設備の調査内容は?特殊建築物調査とどう違うの?
建築設備の対象は換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備、排水設備です。
建築設備の調査内容は特殊建築物調査と同様に、敷地・地盤、建物外部、建物内部、屋根・屋上、避難設備・非常用進入口、その他耐震設備や逃雷設備の項目を調査されます。
調査内容は特殊建築物調査とほぼ同じですが、調査される対象が建物ではなく建物の設備になります。
調査報告は3年に1度の報告で済み、1級・2級建築士の資格を保有していると自身で調査を行い、報告することが可能です。
ですが、特殊建築物調査の特殊建築物調査員資格では建築設備の調査は行えず、建築物調査員の資格が必要になります。
まとめ
特定建築物調査と建築設備の調査の大きな違いは調査の対象です。
特定建築物調査は特定の建物を、建築設備調査は建物の設備を対象に調査が行われます。
1級・2級建築士だと特殊建築物調査と建築物調査を行うことができますが、特定の資格だと特定の対象しか調査をする事はできません。
建築物調査も報告を怠ったら罰金刑に処されるので、指定の期間中に必ず報告するように心がけましょう。