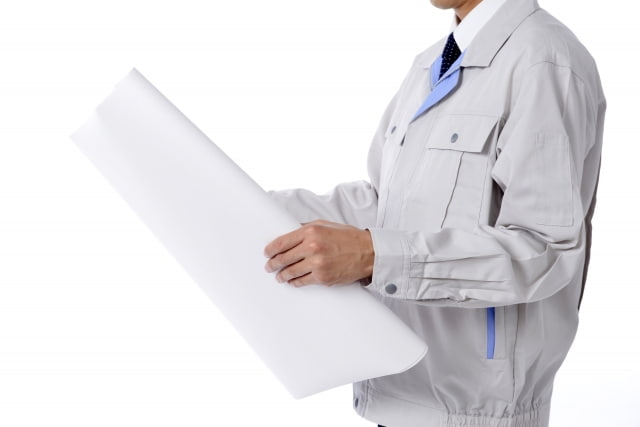特殊建築物の防火設備定期報告の詳細と報告方法
特殊建築物定期調査とは別に、新たに新設された防火設備定期検査は、建物を火事から守るための大切な定期調査です。
今回は、防火設備定期調査に関する詳細を紹介します。
特殊建築物の防火設備定期報告制度の内容
防火設備検査は、2016年の建築基準法改正によって新たに新設された調査項目です。
特殊建築物(特定建築物)として指定された建築物の防火設備に重点を置いた検査で、病院や診療所などの主に公共性の高い建物が該当します。
建築物の定期報告には防火設備定期報告の他に、特殊建築物定期調査報告など様々な調査報告があります。
特殊建築物定期調査報告の中にも防火設備に関する調査報告をしなければいけない項目がありますが、各定期報告によって調査の仕方、調査報告内容が異なっているので、特殊建築物に設置されている防火設備によって防火設備点検定期報告が必要か必要でないかは変わってきます。
定期調査報告制度の改正前は特殊建築物等定期調査報告の中に含まれている「防火設備の設置状況の確認」の項目にそって報告するだけでしたが、基準が緩く、火災時に防火設備がきちんと作動しなかった事故が多く起きたために、詳しく防火設備を点検するために改正後には特殊建築物等定期調査と別に防火設備定期調査が加えられました。
防火設備の定期報告が必要になる対象と消防用設備等点検との違い
防火設備点検が必要になる条件は、調査対象の建物が特殊建築物であることと煙と熱を感知して動作する防火設備があることの2点です。
防火設備点検の対象となる建築物は特殊建築物と呼ばれる劇場や百貨店、ホテル、病院、販売店、体育館、ボーリング場、映画館、共同住宅、事務所などの個人や家族を含め、その他大勢の不特定多数が利用する公共性の高い建物になります。
また、各自治体によっても追加で指定されている建築物があるので、注意が必要です。
防火設備定期調査の対象となる設備は、建築基準法第12条第3項の規定により「火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備」とされています。
この、「火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備」には、主に屋内の面積や防犯区画ごとに延焼防止目的で設置された火災時の避難経路となる臨時閉鎖式防火設備のことを差します。
避難経路となる防火設備には、防火設備用感知器、自動防火扉、手動防火扉、自動防火シャッター、手動防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー、温度ヒューズ式の防火設備等が該当します。
常に閉まっている通常閉鎖式の防火設備や防火ダンパーは防火設備定期調査報告の対象にはなりません。
また、野外や外部に設置されている扉やシャッターは「防犯設備」に該当するので、防火設備定期調査報告の対象にはなりません。
防火設備点検と消防用設備等点検との違いは、火事を防ぐのか知らせるのかの違いです。
消防用設備に該当するのは、自動火炎報知器、複合型の消火設備、発信機、非常灯、地区音響装置が該当します。
どれも、火事が起きたことを知らせるための装置で、防火設備点検に該当する防火のための装置とは役割が異なります。
防火設備の定期報告の調査方法と必要な書類と資格
防火設備定期調査の主な方法は、防火シャッター、防火扉、耐火クロススクリーンなどの駆動装置の稼働確認と、煙熱感知器との連動閉鎖確認、その他危害防止機能の稼働確認です。
特殊建築物の防火設備定期調査は、原則として1年に1回の頻度で調査する必要があり、専門の資格を所持した調査員が調査を行い地方自治体(特定行政庁)に報告します。
防火設備定期調査をすることができる防火設備調査員になるには、1級建築士又は2級建築士、防火設備検査員の国家資格を習得する必要があります。
防火設備定期調査を報告するために必要な書類は、建築物の所在地がある各地方自治体(特定行政庁)のホームページからダウンロードすることができます。
どの地方自治体のホームページでも、検査項目と検査方法の詳細や必要な提出物、作成方法などが詳しく搭載されています。
特殊建築物の防火設備定期調査に必要な書類は、地方自治体によって多少異なりますが、防火設備定期調査報告書2部と防火設備定期調査報告概要、提出リスト、事務手数料を事前振り込みいた際の振り込み書の写しが必要となります。
防火設備の定期報告を提出する方法
提出先は各都道府県によって、地方自治体か業務を委託された一般財団法人かに分かれるので、事前に確認しておきましょう。
できあがった検査報告書は直接自治体に持参するのではなく、郵送で指定の住所に送ることで報告は完了します。
地方自治体によって異なりますが、直接窓口に持参しても受け取ってもらえない地方自治体が多いので注意が必要です。
提出前に、事務手数料を指定の口座に振り込んでく必要があるので、事務手数料を事前に振り込み、振り込みが確認できる写しを提出書と一緒に同封して郵送するようにしましょう。
まとめ
今回は特殊建築物の防火設備定期調査について紹介しました。
防火設備は火事の際に建物を守る大切な設備なので、きちんと毎年調査し、報告する義務があります。
できあがった検査報告書は直接自治体に持参するのではなく、郵送で指定の住所に送ることで完了します。
特殊建築物調査に比べると調査項目は少ないので、比較的簡単に自身で資格を習得して報告することが可能です。
兵庫県の防火設備定期報告制度について
最初に定期報告制度についての趣旨・目的を説明します。
建築物が立ち、長い年月利用していく間に物理的な劣化や補修・改修・部品交換などが必要になると思います。
また、災害や事故などやむを得ない理由で劣化してしまう事があります。
このような事に対応出来る様に、専門家による定期的な調査が必要になります。
これが多数の人々が利用する規模の建築物については、被害の拡大も考えられますし、第三者に危害を及ぼすおそれがあると考え、定期の調査を行い、特定行政庁に報告することを義務付けて安全性の確保を図っています。
その中で、毎年建築基準法に基づき、防火設備に対する調査報告が必要となります。
また平成30年度から建築基準法の法改正に伴い、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員による定期調査報告が必要となります。
定期調査には大きく「特定建築物の定期調査」、「建築設備の定期調査」、「防火設備の定期調査」、「昇降機等の定期調査」の4種類があります。
調査の時期は、兵庫県内の各特定行政庁とも、特定建築物については3年に1回、建築設備・防火設備については毎年1回と定めています。
兵庫県の特定行政庁について
兵庫県内の特定行政庁は、兵庫県、神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市、加古川市、伊丹市、川西市、宝塚市、三田市、芦屋市、高砂市となります。この中で県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。
神戸市を除く特定行政庁は公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターが定期報告業務の委託先として提出窓口となり、神戸市は市が提出窓口となります。
防火設備調査について
2016年6月から建築基準法が改正された事により新設された検査方法となります。特定建築物として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。
調査対象となる建築物は、防火扉・防火・防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを設置されている建築物です。
建築物の所在地を管轄する特定行政庁によっては指定する条件に細かな差異がある為、より詳しく知りたい場合は、特定行政庁の建築指導課に直接問い合わせるか、定期調査業務を委託する調査者に相談してください。
調査内容について
下記それぞれの防火設備により調査方法が異なりますが、建築基準法112条で規定される防火区画について設計図をみながら確認します。
1.防火扉
防火扉の作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
2.防火シャッター
防火シャッターの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
3.耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、機動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
4.ドレンチャー等
作動状態の確認、各部分の劣化・損傷の確認、加圧送水装置の状態確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
定期調査の報告までの流れ
定期報告書の受付・審査・指導の流れについて下記のとおり説明します。
※注意:報告対象年度には特定行政庁(兵庫県建築防災センター)より通知します。
所有者又は管理者 ⇒定期報告書送付 ⇒兵庫県建築防災センター
⇒通知 ⇒各特定行政庁(審査・指導) ⇒審査結果送付
⇒所有者又は管理者
是正すべき事項がある場合は、所有者又は管理者はその内容を専門技術者と相談し、改善に努めていただく事となります。
指示がある場合は、改善計画書・改善報告書を提出する事となります。
まとめ
繰り返しになりますが、防火設備定期調査は、有資格者である、「一級建築士」、「二級建築士」、「防火設備検査員」が行う事となっています。
「一級建築士」は国家試験に合格し、国土交通大臣より免許を受ける事となっています。「二級建築士」は都道府県知事より免許を受ける事となっています。防火設備検査員は資格を満たしているものが講習を修了し、交付を受ける事となっています。
平成28年以降、虚偽の報告に対して、罰則規定も設けられ建物の安全を守る為に定期調査に対して厳格な対応を行うようになってきました。
防火設備、定期調査の内容を正しく理解し、正しい運用を行うように努めていただければと思います。
特殊建築物の防火設備の定期調査とは?点検内容と対象設備
特殊建築物の防火設備は、定期的な調査と報告が義務付けられています。法律で定められた点検内容には、どのような項目があるのか、また、点検の対象となる防火設備について具体的にご説明します。
防火設備の定期調査には建築基準法と消防法の点検がある
a)概要
平成28年度建築基準法の改正に伴い、防火設備の定期調査についても制度が改正されました。この背景には、平成25年10月に福岡県の診療所で発生した火災事故があります。火災発生時に自動的に閉まるはずの防火扉が作動せず、多数の犠牲者が出る痛ましい事故となりました。このような事故の再発防止のために、防火設備は定期調査が強化されました。
点検調査を行う資格があるのは、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防災設備検査員のいずれかの有資格者となります。報告書は、各都道府県の決まった様式で提出することになります。
定期報告の対象建築物は、不特定多数の者が利用する建築物とその防火設備、高齢者や自力避難が困難な物が就寝する施設とその防火設備、エレベーターやエスカレーターなどです。
具体的には下記のような建築物で、床面積や階層が規定の数値を超えるものが対象となります。
・劇場、映画館、演芸場、屋内観覧場、公会堂又は集会場
・病院、診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設
・体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
防火設備の定期調査は、毎年1回の報告が定められています。これは、火災発生時に防火設備が正常に作動しないと、人命に関わる大きな影響を及ぼすためです。平成28年から30年度までの3年間は経過措置として、1回目の報告実施と決められています。
b)建築基準法の点検内容
防火設備の定期調査は、建築基準法の定めと消防法の定めの2種類があります。
建築基準法では、煙感知器や熱感知器、ヒューズ装置、防火扉と防火シャッター、耐火クロススクリーンの点検が定められています。
建築基準法における防火設備の点検は、延焼防止のための防火区画を形成することで、火災発生時に安全に避難できる経路を確保することを目的として、設備が正常に作動するかを確認します。
c)消防法の点検内容
これに対して、消防法では、煙感知器と熱感知器、火災報知機と室内の火災設備や消火器の点検が定められています。
建築基準法と消防法の両方に共通するのは、連動制御器の点検です。
消防法による消防設備の点検は、火災発生を知らせる警報や消火設備が正常に作動するかどうかの点検です。
消防法による点検が設備の正常作動を主としているのに対して、建築基準法における防火設備の定期調査は、人命の安全が最終的な目的となっています。
特殊建築物の定期調査対象となる4つの防火設備
a)防火扉
主に屋内に、延焼防止の目的で設置され、火災発生時には避難経路となります。防火設備の定期調査の対象となるのは、随時閉鎖式の防火扉です。随時閉鎖式の防火扉は、通常解放されており、火災発生時に感知器と連動して閉鎖されるものです。 火災発生時に防火扉が正常に閉まるか点検が行われます。また、扉の閉まり方が強く早いと、人が挟まれて怪我をする危険があるため、防火扉も締まり方について測定が行われます。
一方、常時閉鎖式の防火扉は、普段は閉まっており、通行するときのみ開閉します。こちらは防火設備の定期検査対象外となり、特定建築物の調査対象となります。
b)防火シャッター
防火シャッターは、主に屋内で建物の開口部が大きく、その開口部を閉鎖する必要がある場合、延焼を防止する目的で設置されます。百貨店やショッピングモール、病院施設など、主に大型建築物や複合施設によく見られます。防火シャッターは必要な時だけ閉めるため、常時閉鎖式にはなりません。火災感知器や非常ボタンでシャッターが閉まります。 定期調査の内容として、シャッターの開閉や感知器との連動、シャッターボックスの破損などがないかを点検します。防火シャッターは、シャッターが閉まった際に人が挟まれて怪我をしないよう、危害防止装置のついたものがあります。この装置が正しく動作するかも点検対象です。
c)耐火クロススクリーン
防火シャッターと同様に、屋内で延焼防止のために設置される、天井から閉め降ろすタイプの防火設備です。エレベーターの前や倉庫などで見られ、耐火クロススクリーンの素材はガラス製のクロスです。防火シャッターより耐火クロススクリーンが軽量でペン素材も柔らかいため、人が挟まれる危険性が少ないのが特徴です。
耐火クロススクリーンの点検項目は、感知器との連動と正常に閉まるかどうか、巻取式で開閉するクロスクリーンの場合は、危害防止装置が正常に作動するかも確認します。
d)ドレンチャー
ドレンチャーは、火災発生時に天井部から水が噴射され、水の膜を作って炎や煙が拡がるのを防ぎます。駅や空港など、防火シャッターや耐火クロスクリーンでは対応できない大きな空間に用いられます。
ドレンチャーは、点検であっても実際に水の噴射を作動させることができないため、専門の技術者によって点検が行われます。
以上4種類の防火設備について、定期調査報告では、平面図に対象防火設備の設置箇所を記入し、所有者・管理者の情報や対象建築物の報告書とともに提出します。
まとめ
防火設備は、いざという時に多数の人命を守る重要な役割を担います。多くの人々が利用する大型施設に使用されることも多いため、定期調査により不具合や消耗を発見し改善することは必須です。火災事故を未然に防ぎ、万が一の場合も被害を最小限に抑えることにつながります。